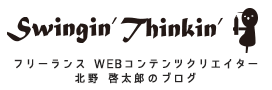お漬物って一年中食べられるイメージがありますが、夏しか食べられない激ウマの漬物があります。
泉州特産の漬物「水なす漬」が、届きました

僕の地元、南大阪の岸和田で暮らす妹夫婦からクール宅急便で「水なす漬」が届きました。
水なすとは、大阪の泉州地域で栽培されている茄子で、よくある長い茄子ではなく、ポテッと丸みをおびた形をしています。その名の通り、水分がたっぷりと含まれていて、そのまま生で食べることもできる茄子のなかでも珍しい品種です。
ぬか漬けで食べるのが一般的で、こうやって、ひとつづつ袋に詰めて売られています。

ぬか袋から取り出した様子。

大きさは、大人の男性の握りこぶしくらい。まずは水洗いで、ぬかを取ります。

手で、サクッと割くことができます。

どうでしょう! このみずみずしさ。
水なす(水なす漬け)は、もともと少し甘みもあるのですが、このジューシーさから「フルーツみたいだ」と、よく言われています。

水なす漬は、簡単に手で割けるので、包丁で切るよりこの方が美味しそうに見えます。上手に割くコツは、へたの部分のみ包丁で切り落とし、上から4分割か6分割の切れ目(ホールケーキのカット状に)を少し入れておくときれいにできます。
まずは、そのままで食し、次におろし土生姜と醤油で食べるのがおすすめです。
僕はこの日、水なす漬けで白ごはんを2杯食べました。最高です!
水なす漬を美味しく食べる方法

- 【1】美味しさの変化を楽しむべし
- 【2】食べる直前に開封すべし
- 【3】包丁は使わず、手で割くべし
- 【4】土生姜、醤油で食すべし
- 【5】酸っぱくなれば、刻むべし
妹夫婦は、伊勢屋漬物店の水なす漬を送ってくれたのですが、その箱の中に、このような食べるコツが書かれて用紙が入っていました。
水なす漬けは、ぬか床に漬けますが、浅漬けで食べるのが一般的です。ですが、伊勢屋さんの解説によると、「一日一日の変化を楽しめ!」とあります。五日目以降になると、早くも古漬けの味わいになり、少し酸味が出てきます。その頃になれば、包丁で刻んで食べると良い、のだそうです。

私事ですが、僕の亡くなったおばあちゃんは、茶粥と水なすの古漬けを好んで食べていました。あと数日後にはその頃合いになるので、茶粥と水なす、やってみようかなぁ。